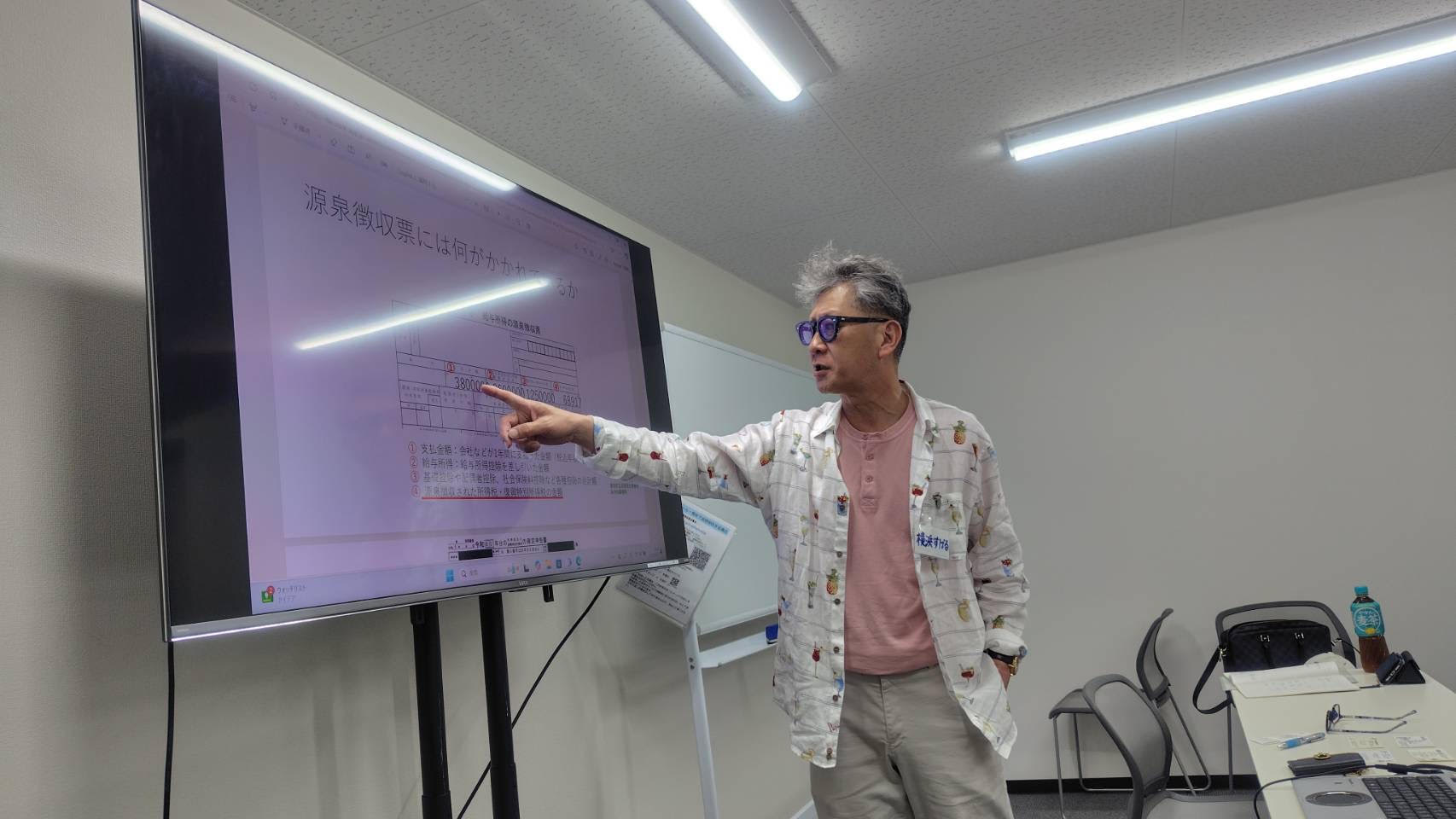試験は必ず受験しましょう
いよいよ技術士二次試験が始まります。
今年は7月20日(日)が総合技術監理部門の必須科目、翌日21日(土)は総合技術監理部門を除く技術部門及び総合技術監理部門の選択科目になります。
毎年技術士二次試験申込者の4分の1が試験を受験しません。
「どうせ不合格だから受験するのを止めよう」とか「今年は準備が不十分だから受験するのを止めよう」という動機で受験を断念するようです。
どうせ不合格かもしれませんが、最終的に技術士を目指すのであれば必ず受験してください。
不合格かもしれませんが全力で試験に挑んでください。
必死で考えて、必死で解答用紙を埋めてください。
必死になれば、そこから何かが得られるはずです。
「一生懸命だと知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、いい加減だと言い訳が出る」は、武田信玄の名言です。
この言葉は、物事の取り組む姿勢の大切さを教えています。
一生懸命に取り組むことで、問題を解決するための知恵やアイデアが生まれます。
しかし、中途半端な姿勢では愚痴ばかりが出て、前に進むことができません。
さらに、いい加減な態度では、言い訳をすることで自分を誤魔化してしまいます。
私の知り合いで、試験勉強をほとんど何もせずに合格している人がいます。
ひとりやふたりではなく数十名います。
受験すれば結果は合格か不合格です。
運が良ければ技術士の称号を得られます。
しかし受験しなければ絶対に技術士の称号を得られません。
合格者の10%はまぐれで合格しています。
受験しないというのはもったいない話です。
技術士二次試験に申込みした方は必ず受験してください。
技術士合格は今からでも間に合う
技術士二次試験の合格は今からでも間に合います。
試験まで残り1カ月が、一番学力が上がります。
必死で勉強した成果が指数関数的に上がってきます。
今からでも合格に間に合う方法を教えます。
建設部門必須科目
横浜すばる技術士事務所から販売している「必須科目予想問題」を購入してください。
予想問題3問とその模範解答を載せています。
問題と模範解答をよく読んで理解してください。
理解できたら、模範解答を暗記してください。
暗記するといっても、一字一句丸暗記するのではありません。
模範解答の「流れ」を暗記してください。
言い換えれば「内容を覚える」ということです。
同じ問題は出題されることはありませんが、同じような問題は出題されます。
内容を覚えた論文を加工して、問題文の題意を満たすように書いてください。
この方法でA判定は取れます。
これを「カレーライス理論」と言います。
カレーライス理論の詳細はこちらから。
必須科目は高得点を取る必要はありません。
合格点である60%以上を得点すればいいだけです。
建設部門選択科目
選択科目も同じ問題は出題されませんが、同じような問題は出題されます。
勉強の仕方は必須科目も選択科目も基本的に同じです。
カレーライス理論を活用してください。
横浜すばる技術士事務所から販売している「合格する論文の黄金法則」をご購入してください。
自分の選択科目の問題と模範論文を3年分くらい暗記してください。
必須科目と同じで、暗記するといっても、一字一句丸暗記するのではありません。
模範解答の「流れ」を暗記してください。
内容を覚えてください。
選択科目も毎年少しずつは変化しますが、大きな変化はありません。
解答の方向性が間違っていなければ、今からでもA判定の論文を書くことは可能です。
「合格する論文の黄金法則」の詳細はこちらから。
技術士二次試験は「考え方」を問われる試験
技術士二次試験は、受験生が普段何を考えているかを問われる試験です。
問われていることは毎年似通っています。
自分の専門分野の将来の課題とその解決策を問われます。
それに加えて、その解決策の取り扱い上の注意事項です。
その辺りの考え方を論理的でわかりやすく書ければ合格します。
合格する論文のコツが分かれば合格するのです。
そのコツをつかむ一番早い方法が「カレーライス理論」なのです。
技術士を何部門も取得されている方や、大した勉強もしていないのに一発で合格している人はこの「カレーライス理論」を実践しています。
一方でそれなりに勉強しているのに、なかなか合格しない人は自分でオリジナルの解答を書こうとしています。
オリジナルが悪いわけではありませんが、解答の方向性を確認していない方を多く見かけます。
解答の方向性が間違っていると合格点はもらえません。
解答の方向性とは、問題文の「題意」に答えているか否かです。
たとえば問題で東京から大阪に行く方法を問われているのに、東京から仙台に行く方法を書いているような解答です。
この場合はどのような方法を書いても大阪に行けません。
大阪に行けないので、新幹線のグリーン車で行こうが、飛行機のファーストクラスで行こうが結果は不合格になります。
一方徒歩であろうが自転車であろうが、大阪に確実に行けるのであれば大きな減点はされません。
大きな減点が無ければ最低でも合格点は取れます。
大阪に行く方法を考えてみます。
飛行機、新幹線、在来線を乗り継ぐ、バス、自家用車、バイク、ヒッチハイク、自転車、徒歩とします。
この交通手段が自分の覚えた模範論文になります。
交通手段が多ければ多いほど、状況に合わせて大阪に行く方法が多くなります。
自分の覚えた模範解答が多ければ多いほど、どのような問題にも対応可能になります。
合格する論文を書くのは、東京から大阪に行く方法と同じなのです。

メルマガ登録はこちらから