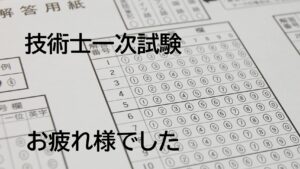技術士二次試験筆記試験が終了しました
技術士二次試験筆記試験が終了しました。受験された方はお疲れさまでした。
この試験は申込者の20~30%程度は、毎年受験せずに技術士になることをあきらめています。
それだけ難易度が高く、簡単に合格できないことが前提となっています。
合格の反対は不合格ではありません。
受験しないことです。
受験すれば運がよければ合格します。
あとは神のみぞ知るです。
毎年合格者の10%程度はまぐれで合格しています。
次のステージに向けて計画を立て、万全な準備をしましょう。
さぼる計画を立てること
しばらくは受験勉強から解放されて休んで頂いても構わないと思います。
技術士2次試験は筆記試験で終わりではありません。
次は口頭試験が待ち受けています。
口頭試験に合格してはじめて技術士になれる資格を得るのです。
休む前に計画的にサボる必要があります。
筆記試験が終わり一息つく前に次の2つのことを行ってください。
最初にすべきことは、再現論文を作成すること
論文を再現する理由は2つあります。
理由①合否の要因を探るため
不合格の場合にはどこが悪かったのか?
合格した場合にはどこが評価されたのか?
これを分析するために再現論文を作成します。
試験当日の記録がないと客観的な合否の要因がわかりません。
受験したすべての解答に対して、論文の再現するようにしてください。
今年不合格だったとしても、来年合格するためには不合格の要因を探る必要があります。
再現論文がないと、何が悪いのか?どのように対応していいのか?何が足りないのか?
などが全くわかりません。
最終的に合格したいのであれば、必ず解答を再現するようにしてください。
理由② 口頭試験で筆記試験の記述内容を聞かれる場合があるため
特に総合技術監理部門は、筆記試験の内容について諮問される場合が他部門より多くあります。
この講座の受講生の方も、過去に何人か筆記試験の内容を諮問された方がいました。
間違っても自分が記述した内容に対して「忘れました」とは言いたくないモノです。
記憶が鮮明なうちに受験した論文のすべてを再現するようにしてください。
再現した論文があれば、口頭試験で聞かれる内容も推測できます。
再現した論文がなければ、口頭試験で聞かれる内容も推測できません。
口頭試験の合格を確実にするためにも、論文の再現は必ず作成しましょう。
休むための計画を立てること
いつから受験勉強を再開するのか?
どのように勉強するのか?
何を勉強するのか?
いつまでサボるのかを計画を立ててから休んでください。
なぜサボる計画を立てるのか?
それは計画がないと、永遠に休んでしまうからです。
7月18日に筆記試験が実施されました。
合格発表は10月下旬です。
口頭試験は12月上旬から1月中旬です。
筆記試験合格発表から口頭試験まで短いヒトで準備期間が1カ月しかありません。
筆記試験の合格を知ってから、口頭試験の対策に取りかかっても遅いのです。
遅くとも10月からは口頭試験対策をはじめましょう。
必ず合格するという高い意識を持つこと
ある程度の下準備が必要になります。
筆記試験の合格発表の前から準備する必要があります。
合格を知らないうちに口頭試験の準備をするのはモヤモヤしてイヤなものです。
口頭試験対策をするのは苦痛かもしれませんが、
技術士になるためには通らなければならない道です。
いつから勉強するのか?
その計画を立ててから休むようにしてください。
筆記試験の合格率は10%程度です。
口頭試験の合格率は90%程度です。
口頭試験の合格率は非常に高くなります。
非常に高いので不合格になった時のショックは計り知れないものがあります。
口頭試験では必ず10%の受験生が不合格になります。
毎年10%の受験生が涙を飲みます。
不合格になる一番の理由は準備不足です。