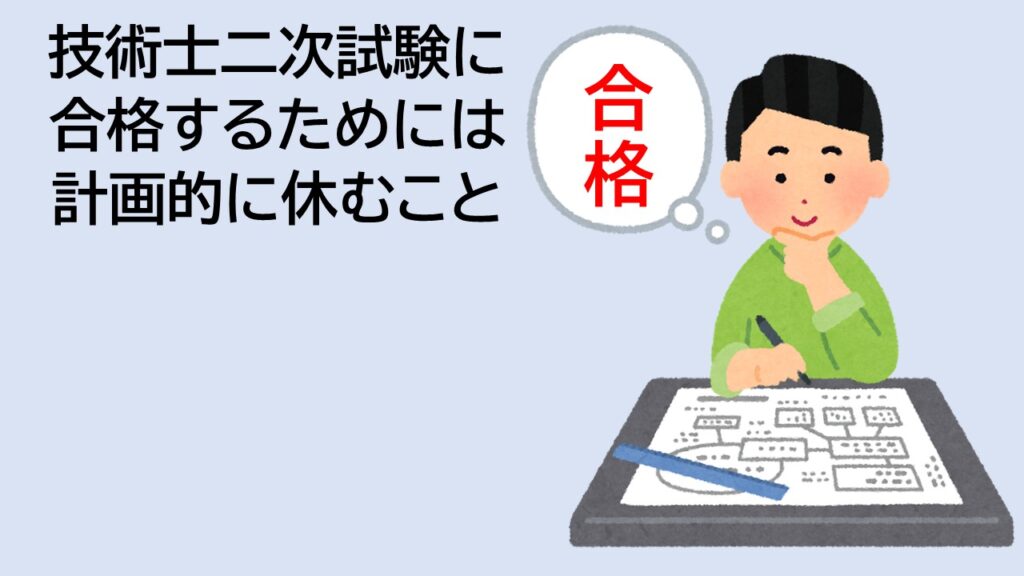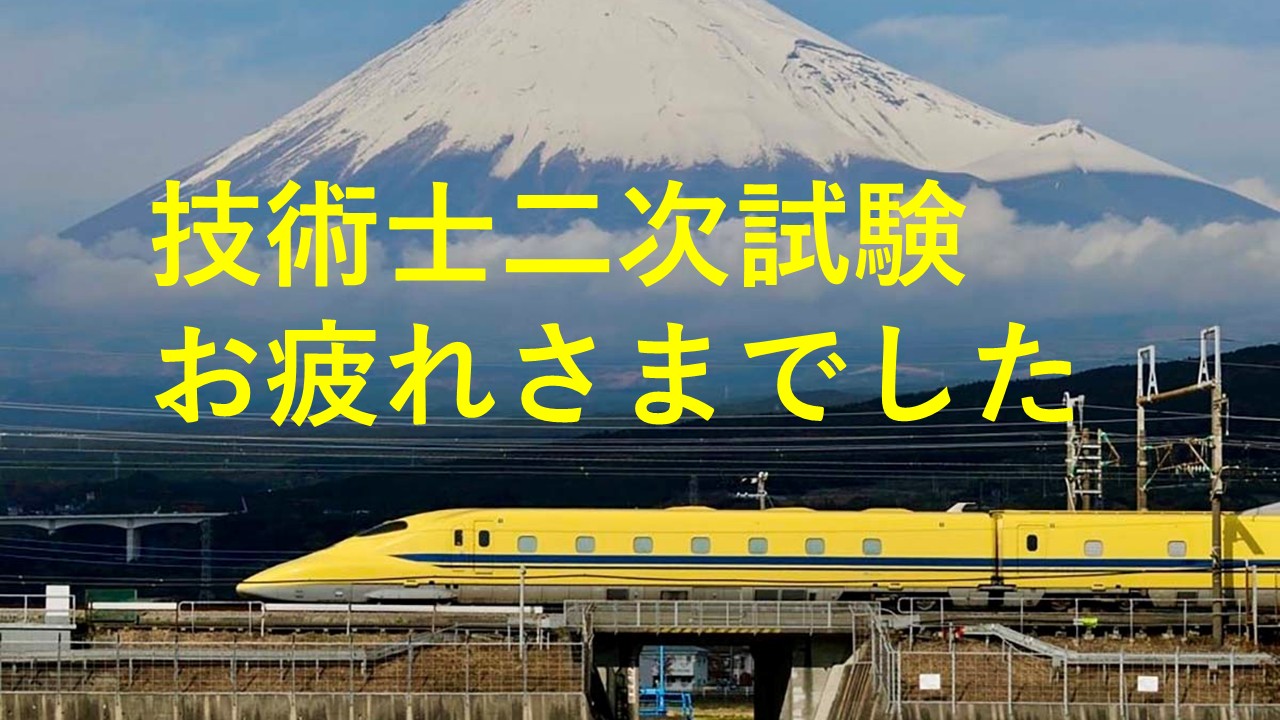技術士二次試験が終了しました
令和7年度技術士二次試験が7月20、21日に実施されました。
受験された方はお疲れさまでした。
1日で600字詰め原稿用紙を9枚書く試験です。
非常にハードな試験です。
まずは無事に試験を受験できたことに感謝して、夏休みを楽しんで頂きたいと思います。
皆さん同じだと思いますが、この試験は色々と時間とお金を使います。
家族の協力なしに受験することは難しいと思います。
少し奮発して家族においしいものでも食べさせてあげてください。
技術士二次試験が終了したといっても、筆記試験が終了しただけです。
合否はまだわかりませんし、合格していたら口頭試験が待っています。
不合格の場合は、また来年筆記試験からやり直しです。
計画性を持って次のステージに進んで頂きたいと思います。
再現論文を作成する
筆記試験が終了したら、必ず再現論文を作成してください。
自分の解答を情報として残せるか否かは非常に重要です。
理由は色々ありますが、重要なものは以下の3点です。
■不合格の原因追及
■口頭試験で聞かれる場合がある
■自分の欠点の確認
不合格の原因追及
不合格の論文には必ず減点された理由があります。
なぜ不合格になったのかが分からないと、来年も同じ過ちをして不合格になります。
来年も再現論文を作成しないと再来年も不合格になります。
それを永遠に続けることになります。
「どうせ不合格だから、論文を再現する気にはなれません。」という人がいます。
そのような人に限って、不合格になると落ち込むのです。
丸1日を費やして受験した試験です。
論文の再現はパソコンで再現すれば、2時間程度で終わるはずです。
せいぜい3時間あれば再現論文は作成できます。
その3時間をケチると、来年も不合格になります。
この試験は基本的に難しくありません。
①問題文を読んで、問題文で要求されていることを書くこと
②その内容が間違ってないこと
③内容が読んで理解できること
④文字数を満たしていること
基本的に上記の4点を守れば点数の引きようがないのです。
自分の論文は上記の4点のどれに該当するのかを確認するためにも、再現論文は必ず作成しましょう。
口頭試験で聞かれる場合がある
筆記試験の内容について、ごく稀ですが口頭試験で聞かれる場合があります。
一般部門では稀ですが、総合技術監理部門はたまに聞かれています。
直接口頭試験の合否には関係しません。
何かのきっかけの1つとして聞かれる場合があります。
口頭試験で筆記試験の解答を尋ねられた場合に「知りません」「忘れました」とは言いたくはないでしょう。
筆記試験で誤った内容があった個所を指摘されたとします。
再現論文を作成しておけば、挽回ができます。
好印象を与えることもできます。
その結果として口頭試験に不合格になる可能性は低くなります。
口頭試験のリスク低減対策として筆記試験の解答を再現しておきましょう。
自分の欠点の確認
筆記試験の解答を再現しているうちに自分の答案のミスを発見できる場合があります。
私の場合もそうでした。
間違った知識で解答したことがありました。
結果的に合格だったのですが、事前に自分のミスに気が付き、よかったと思っています。
講座の受講生でも、再現論文を作成中に普段講師からよく注意されているミスに気が付いた方がおられました。
その年は不合格でしたが、翌年は合格しました。
試験本番では時間に追われ、必死になって解答しています。
再現論文の作成中は、冷静に自分を俯瞰して解答を再現することができます。
その時に自分のミスを認知できれば、たとえ結果が不合格だったとしても収穫は大きいです。
理由はメタ認知の能力がみについたからです。
メタ認知とは、自分を客観的にみる能力のことです。
技術士二次試験を何回受験しても不合格になる人は、このメタ認知能力がありません。
反対に技術士二次試験を1回で合格してしまう人は、メタ認知能力に長けています。
「自分は出題者の意図をくみ取って論文を解答しているだろうか?」
と常に自分の「考え」と「行動」を疑ってみてください。
再現論文を作成するとこの能力を身につけられる訓練になるのです。
休む時は計画的に休む
人はなにか行動するときには、計画を立てます。
なぜ計画を立てるのかといえば、目標を達成するためです。
目標を達成する計画を立てて、計画通りに行動すれば合格するのです。
ただしこれは計画が正しいという前提に立っています。
反対に休む時に、休む計画を立てる人はあまりいません。
これは非常に危険な状態です。
休む時にいつまで休むのかを計画しないと、永遠に休み続けるのです。
筆記試験の合格発表は11月上旬です。
口頭試験は早い人で12月上旬から始まります。
準備期間が1か月しかないのです。
技術士の称号が欲しいのであれば、いつから口頭試験対策を行うのか計画を立てましょう。